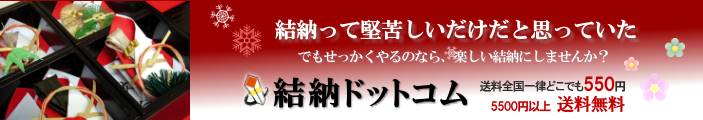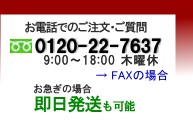| Q:結納金のお返しはないんだけど、形として同時交換にしたい、良い方法はないでしょうか? |
|
A:例えばこの同時交換プランのような、色違いで同じ結納セットをまず揃えます。男性側からは普通通り、結納金を包みます。
女性側からは袴料としてのお返しのお金がないので、代わりに結納の受書(受領書)を、本来袴料を入れるべき袋に入れてしまうんです。
| Q:関東で一般的な半返しの分を差し引いて結納金を頂くためお返しの袴料がない、一応彼への記念品はあるので形として何とか同時交換にしたい |
|
A:この場合も上記の方法で対応できると思います。でも上記のような方法ではなく、記念品だけを、お返しでされる方もありますよ。
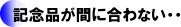
| Q:洋服をオーダーしたんだけど、なんと当日に間に合わないことが判明、どうしよう・・・ |
|
A:この場合、下記の図のように洋服の代わりに“その分のお金を土産料として包む”のが良いのではないでしょうか。「洋服料」または「背広料」などの名目にし、袋を記念品飾りの上に置いておきます。
また次に右上でご紹介する“目録を付ける”と言うのも良い方法だと思います。
★背広以外の品物でも対応できます。
★結納飾りと同質の和紙でお作り致します。
★その旨相手様には、口頭でもお伝えください。
 (a0413)袋(お土産料) (a0413)袋(お土産料)  
★ここでご紹介している、多少イレギュラーな方法も両家が了解の上ならOKですよ。
|
|
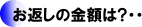
女性側からは通常結納金の10%程度を袴料としてお返ししますが、結納金の金額が分からないことには一体いくら包んだら良いのかわからないと言う事態が時々発生します。事前に話し合いなどができるといいかもしれないですね。
→「小袖料」「袴料」の意味
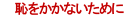 → こちら → こちら
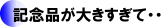
| Q:記念品が大きくて、結納をするレストランに持ち込むのが難しいんだけど・・・ |
|
A:この場合ズバリ → 目録のみ付ける
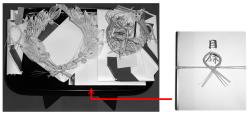
目録は下に敷いてあります
 (a0206) 目録(台なし)A (a0206) 目録(台なし)A  
 略式のタイプで、目録をオプションでつけた場合の目録の配置は、あまり見た目が大げさにならないようにとお考えのお客様が多いことから、上の写真のように下に敷くか、目録だけ手渡しでお渡しするようにおすすめしています。 略式のタイプで、目録をオプションでつけた場合の目録の配置は、あまり見た目が大げさにならないようにとお考えのお客様が多いことから、上の写真のように下に敷くか、目録だけ手渡しでお渡しするようにおすすめしています。
でもやっぱりちょっと窮屈かな?と言う場合、目録用にもう一台、台を追加して配置することも可能

| 目録を乗せるために一般に使用される台は、左の写真のような「ヘギ台」と呼ばれる簡略な木製台。足なし、24cm正方形 |
 |
 (a0208)目録(台付)A (a0208)目録(台付)A  
A:結納が終わった時点で結納返しをゴソゴソと並べるのはスムーズな結納式の進行という点からみると×。最初から二つとも並べておいたほうが良いと思います。
|